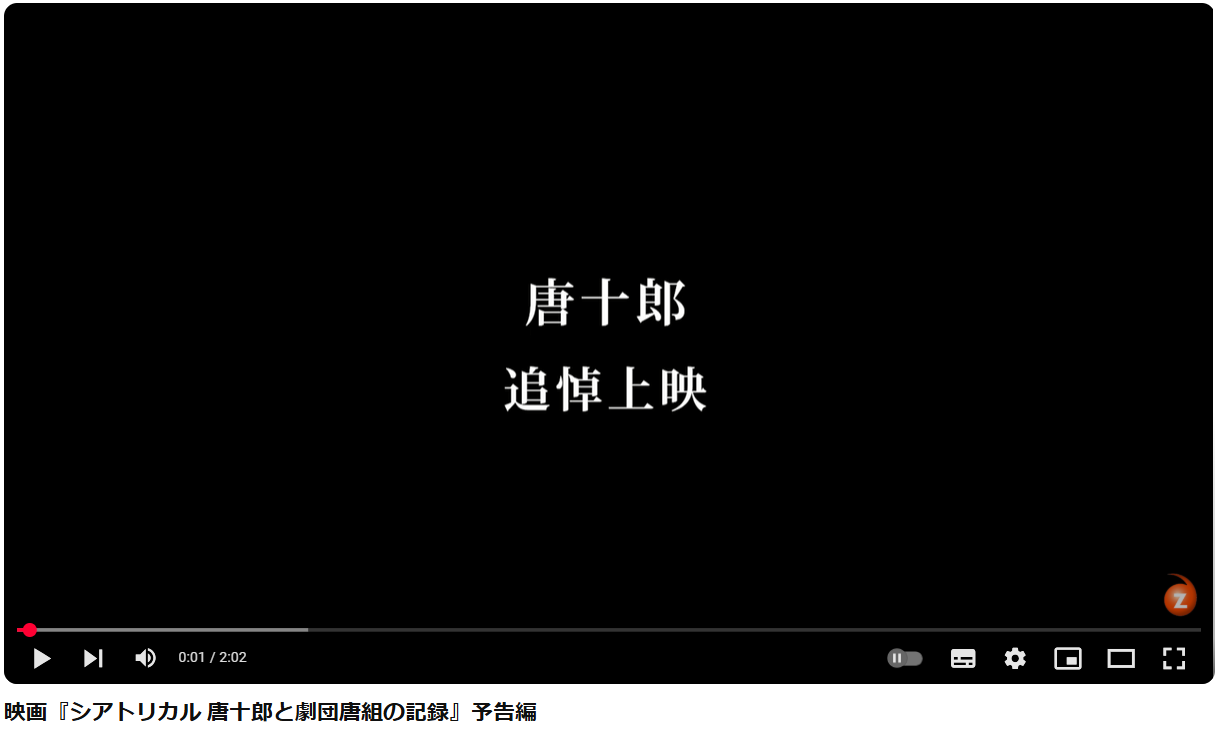「暮らし」という言葉は、日常生活や日々の営みを指す言葉です。具体的には、住む場所や食事、仕事、家族との時間など、人が日々の生活を送るために行うすべてのことを含みます。
日本語で「暮らし」という言葉を使うときは、単なる物質的な側面だけでなく、心の満足や生活の質、幸福感なども含めて、広い意味での日常のあり方を表現することが多いですね。人生も、「暮らし」に関連される言葉になるようです。
💞 恋愛が「暮らし」に含まれる理由
恋愛は単なる「特別なイベント」ではなく、日々の会話、食事の約束、通勤中に考えること、休日の過ごし方など、日常そのものに溶け込む関係です。こうした行動はすべて「暮らしの一部」として続いていくものです。
「住まい」という言葉を使う際には、居住している場所そのものに対する思いや、そこに住むことで得られる安心感や快適さといった感情も含まれることが多いです。
たとえば、「心地よい住まい」や「住まいを整える」といった表現は、単に建物だけでなく、その場所での暮らしや快適さを大切にする意味合いが込められています。
古い賃貸住宅に住むことには多くの魅力と課題がありますが、それを楽しみながら快適に生活する方法もたくさんあります。
※当ブログは、Amazonアソシエイトとして適格販売により収入を得ています。また、第三者配信の広告サービスを利用しています。
※その時々に、フリー素材(写真)・AI生成画像を使用しています。
シアトリカル 唐十郎と劇団唐組の記録
真実か、白昼夢か
追悼 唐十郎/17年ぶりの再上映
ドキュメンタリーという名のホラー
唐的妄想大爆発!1967年、新宿・花園神社の紅テント公演で、演劇界に革命的な衝撃を与えた天才劇作家・唐十郎。それから40年、67歳になっても芝居に対する情熱は衰えることを知らず、唐は自らを「偏執狂」と呼ぶ。2006年秋の新作戯曲執筆から2007年春の公演初日までを追った今回のドキュメントには、芝居作りに賭ける唐のすさまじい「偏執」ぶりがありありと描き出される。
唐十郎 kara juro
劇作家・演出家・俳優 1940年生。1964年、劇団「状況劇場」を率い劇作家デビュー。70年代にかけて大ブームが起きる。状況劇場出身の主な俳優は、李麗仙、麿赤児、根津甚八、小林薫、佐野史郎ら。1970年「少女仮面」で第15回岸田國土戯曲賞受賞。作家としても活躍し、1983年「佐川君からの手紙」で第88回芥川賞受賞。1988年、状況劇場を解散、劇団唐組を設立。2004年「泥人魚」で第38回紀伊國屋演劇賞・第7回鶴屋南北戯曲賞・第55回読売文学賞を受賞。2006年、読売演劇大賞芸術栄誉賞受賞。2024年5月4日、逝去。
20歳のころ、人生の岐路に立った時期がありました。当時、私は進路について深く悩み、苦しんだ時期でした。好きな小説を読んでいる時だけが、癒されている状況だったのです。
生きていることへの苛立ちと言えばよいのでしょうか。当時のことを思い出してみても、複雑な心境が駆け巡ってゆくばかりで、上手く書き記すことができないと思います。ただ言えることは、書物の中で出会った見ず知らずの著者、例えば「寺山修司氏」や「唐十郎氏」の著作や演劇活動を垣間見て、生きることへの希望を見いだしたことです。良い意味で刺激を受けていました。
だから、このブログは備忘録として記しているつもりです。けれども、このブログは単なる「創作日記」のようなものでしかないように思えるのです。
しんいちが角膜移植で手に入れた片目。ある日この眼の前の持ち主の恋人くるみが現れる。しんいちの意思に反して反応する眼。それは闇ルートで買った「ジャガーの眼」と呼ばれるものだった。 「肉体の一部を追うものはなく、まして追われようとする肉体の一部もない。」とDr弁は言うが・・・・・。
Audible(オーディブル)は、プロのナレーターが朗読した本をアプリで聴けるサービスで、「聴く」読書になります。Audible会員なら定額で12万以上の対象作品を聴き放題。※30日間の無料体験を試してみる。詳細は下記のURLをクリック!!