「暮らし」という言葉は、日常生活や日々の営みを指す言葉です。具体的には、住む場所や食事、仕事、家族との時間など、人が日々の生活を送るために行うすべてのことを含みます。
日本語で「暮らし」という言葉を使うときは、単なる物質的な側面だけでなく、心の満足や生活の質、幸福感なども含めて、広い意味での日常のあり方を表現することが多いですね。人生も、「暮らし」に関連される言葉になるようです。
💞 恋愛が「暮らし」に含まれる理由
恋愛は単なる「特別なイベント」ではなく、日々の会話、食事の約束、通勤中に考えること、休日の過ごし方など、日常そのものに溶け込む関係です。こうした行動はすべて「暮らしの一部」として続いていくものです。
「住まい」という言葉を使う際には、居住している場所そのものに対する思いや、そこに住むことで得られる安心感や快適さといった感情も含まれることが多いです。
たとえば、「心地よい住まい」や「住まいを整える」といった表現は、単に建物だけでなく、その場所での暮らしや快適さを大切にする意味合いが込められています。
関連ブログ記事
「詐欺=お金の問題」だけじゃなくて、心を裏切られるショックの方も深刻だなと思います。一気に不信感や自己否定につながってしまう…。だからこそ社会全体で声を上げて、注意喚起をし続けるのってすごく大事だと感じます。
※当ブログは、Amazonアソシエイトとして適格販売により収入を得ています。また、第三者配信の広告サービスを利用しています。
※その時々に、フリー素材(写真)・AI生成画像を使用しています。
何者かが有名人の動画を勝手にAIで作り替え、「SNS型投資詐欺」に悪用するケースが急増しています。 経済アナリストの馬渕磨理子さんは、自身のニセ動画がSNS上に広がり、対応に苦悩しているといいます。 今年すでに4700件以上、被害額にして600億円を超える投資詐欺。なぜ、人はだまされてしまうのでしょうか? 『サン!シャイン』は、1400万円をだましとられた男性を取材。 巧妙な手口を見分ける方法はあるのでしょうか? (「サン!シャイン」2025年10月9日放送)
「YouTubeに著名人の生成AI動画が…」投資詐欺の被害女性語る驚きの手口
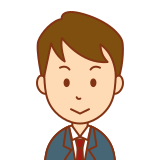
何者かが有名人の動画を勝手にAIで作り替え、「SNS型投資詐欺」に悪用するケースが急増しています。それについて、注意喚起になるようなことを教えてください。
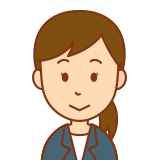
いい質問です。こういう「有名人の動画を AI やディープフェイクで改ざんして、投資勧誘などに使う詐欺」は、近年大きなリスクになってきています。以下は、注意喚起として知っておくべきこと、見分け方、対策などを整理したものです。
1. 詐欺の手口・実例(参考になるもの)
まず、実際に使われている手口を知っておくと、怪しい兆候を見抜きやすくなります。
- 有名人や著名人(起業家、芸能人、投資家、ジャーナリストなど)の顔と声を AI で合成した動画広告を SNS に流し、「この人が○○で儲けた」「すぐこの投資を始めよう」などと勧誘するケース。 (Trend Micro News)
- その広告から “限定の投資グループ(例:WhatsApp、Telegram、LINEグループ等)に誘導” → グループ内で巧みに信頼を築き、少額投資 → 利益報告 → 次第に大きな金額を出資させる。 (カスペルスキー)
- 実在のニュース記事やメディアを改ざんしたような体裁を取り、「○年で100倍」「有名人が使っている」といった虚偽情報を混ぜ込む。 (ガーディアン)
- 音声クローン(声を AI で模倣)を使い、電話やライブ通話で本人になりすますケース。 (makecentsmakesense.nebraska.gov)
- 企業幹部や上司になりすまして、社内決裁権者をだまして資金を不正送金させる “ビジネスの中でのディープフェイク詐欺”。例えば、AI で上司の声を合成して、緊急性を装って送金を指示させた、という報告もあります。 (フィナンシャル・タイムズ)
- 世界的にも被害は深刻で、2024年には AI を悪用した詐欺で数十億ドル単位の被害が報告されているという調査もあります。 (McAfee)
2. 見分けるためのチェックポイント(レッドフラッグ)
こういう詐欺を見抜くために、次のような点を常に疑ってみることが重要です。
| チェック点 | 内容 | なぜ怪しいか/注意点 |
|---|---|---|
| 非常に高い確約的な利回り・保証 | 「必ず儲かる」「年率○○%確約」などを謳っている | 投資には必ずリスクがあるため、“保証”を謳うものは詐欺の可能性高し (New York State Attorney General) |
| 急いで投資させようとする | 「今しかない」「限定10名」「早く決めないと参加できない」など | 焦りを煽って考える時間を奪う典型的手口 |
| 有名人の名前・顔・声を使っている | 「〇〇も使っている」「あの有名人が推薦している」等 | 本人の公表がないなら疑ってかかるべき。ディープフェイクや無断使用の可能性あり |
| 投資プロモーションが SNS 広告を通している | 特に広告からディレクトリンクで誘導してくる | SNS 広告・投稿は審査が十分でない場合が多く、偽情報が拡散しやすい (カスペルスキー) |
| 投資話を “非公開グループ” やチャットアプリへ誘導 | 公の場ではなく、LINE/WhatsApp/Telegram などへの誘導 | 外部からの監視ができず、コントロールされやすい/抜けにくい状況を作るため |
| 出資後の引き出しに制約がある | 手数料・税金・本人確認・規制の名目で追加資金を要求される | 詐欺は最初は小さく始まり、徐々に被害を大きくするパターンが多い |
| 情報源の信頼性が低い | 宣伝リンク先が公式サイトではなく、URLが不自然、評判がない | ドメイン・SSL 有無・運営者情報を確認すべき |
| 本人が否定している | 被害報道や本人から「自分はそんなことは言っていない」という発表がある | 詐欺側は否定できないような証拠を隠すことが多い |
3. 防止・対応策(何をすればいいか)
注意を喚起するだけでなく、実際に対策をとることが大事です。
- 一次情報を確認する
有名人や関係者の公式サイト、公式SNS、信頼できる報道機関でその投資の推薦があるか調べる。
本人が否定声明を出していないかもチェック。 - 広告・投稿は鵜呑みにしない
SNSで見た広告は「宣伝」の可能性を常に疑い、広告の出所、運営元を確認。
いいね数やシェア数だけで安心しない。 - 急かされても冷静に対応
「今すぐ申し込め」など急かす誘いには乗らず、一度自分で時間をとって調べる。
信頼できる第三者(金融機関、投資の専門家、知人など)にも相談。 - 契約と法的な確認
投資するなら、契約書や運営者の登録番号、所在地、実績などを確認。
金融商品取引業などの登録があるかどうかを確認。 - 少額から始める
もしどうしても興味があって始めるときは、最初は小さい額からにして、引き出しやすさを試す。 - 記録を残す
勧誘のスクリーンショット、動画、チャット履歴を保存しておく。後で警察や消費者相談窓口に相談するための証拠になる。 - 不審なものは報告・通報
詐欺だと感じたSNS広告やアカウントをプラットフォームに通報する。
警察や消費者センター、金融庁、国の詐欺対策部署などにも相談。 - 啓発・情報共有
家族や友人、特に年配の方など、ネット投資に不慣れな人にこのような詐欺の危険性を伝える。
SNSでも注意喚起を広める。

Audible(オーディブル)は、プロのナレーターが朗読した本をアプリで聴けるサービスで、「聴く」読書になります。Audible会員なら定額で12万以上の対象作品を聴き放題。※30日間の無料体験を試してみる。詳細は下記のURLをクリック!!










