「暮らし」という言葉は、日常生活や日々の営みを指す言葉です。具体的には、住む場所や食事、仕事、家族との時間など、人が日々の生活を送るために行うすべてのことを含みます。
日本語で「暮らし」という言葉を使うときは、単なる物質的な側面だけでなく、心の満足や生活の質、幸福感なども含めて、広い意味での日常のあり方を表現することが多いですね。人生も、「暮らし」に関連される言葉になるようです。
💞 恋愛が「暮らし」に含まれる理由
恋愛は単なる「特別なイベント」ではなく、日々の会話、食事の約束、通勤中に考えること、休日の過ごし方など、日常そのものに溶け込む関係です。こうした行動はすべて「暮らしの一部」として続いていくものです。
「住まい」という言葉を使う際には、居住している場所そのものに対する思いや、そこに住むことで得られる安心感や快適さといった感情も含まれることが多いです。
たとえば、「心地よい住まい」や「住まいを整える」といった表現は、単に建物だけでなく、その場所での暮らしや快適さを大切にする意味合いが込められています。
実際、「マンションの管理会社・設計コンサルタントと施工業者との癒着」「談合」によって、相場よりも高い見積もりが通される可能性は、業界でも指摘されており、無視できないリスクとされています。ただし「全般的にそうだ」という証明にはなっておらず、個別ケースごとに注意深く判断する必要があります。

※当ブログは、Amazonアソシエイトとして適格販売により収入を得ています。また、第三者配信の広告サービスを利用しています。
※その時々に、フリー素材(写真)・AI生成画像を使用しています。
マンションの管理会社は特定の修繕工事会社と癒着し、談合によって相場より高い見積もりを出している。それを証明するように今年3月、公正取引委員会は修繕工事会社20社に対し独禁法違反容疑で立入検査を開始した
マンション管理 建替え・修繕 徹底ガイド 2025年版(日経ムック) (日本経済新聞出版) Kindle版
建替え or 長寿命化――どうする!? 老朽化マンション
新制度やDXで変わる、マンション管理組合の新しい取り組み
築40年を超える老朽化マンションは2022年末に125.7万戸に増え、国内の分譲マンションのストック総数の約18%に達しました。こういったマンションに暮らす住人の約半数は60歳以上の高齢者世帯で、管理組合は建物と住人の「2つの老い」の課題を抱えています。
マンションの修繕計画の結果を表示しています
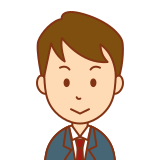
関連した別の質問になりますが、「マンションの管理会社が特定の修繕工事会社と癒着し、談合によって相場より高い見積もりを出している場合がある」らしいのですが、実態はどうでしょうか。
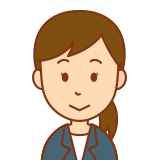
いい質問です。実際、「マンションの管理会社・設計コンサルタントと施工業者との癒着」「談合」によって、相場よりも高い見積もりが通される可能性は、業界でも指摘されており、無視できないリスクとされています。ただし「全般的にそうだ」という証明にはなっておらず、個別ケースごとに注意深く判断する必要があります。以下に、実態・典型的な手口・証拠リスク・防止策を整理します。
実態と最近の動き
1. 公正取引委員会の調査実例
- 2025年3月、公取委がマンション大規模修繕工事に関わる施工業者約20社を対象に立ち入り検査を実施したという報道があります。(ダイヤモンド・オンライン)
- その後、対象業者が30社超に拡大したとの報道もあります。(横浜マンション管理・FP研究室)
- 報道では、大手リフォーム会社や建装工業なども調査対象になっている、という指摘がなされています。(ダイヤモンド・オンライン)
これらの調査の背景には、「複数物件で不自然な入札価格」「同一業者の継続受注」「特定のコンサルタントが推奨する業者」などの疑念があった、という報道もあります。(center-office.com)
つまり、実際に行政が動き出している事例が最近出てきており、過去の理論ではなく「現実のリスク」として注意すべき段階に来ている、という見方ができます。
2. 指摘されている癒着構造・談合のパターン
いくつか典型的な手口・構造が業界関係者・報道で指摘されています:
| 手口 | 概要 |
|---|---|
| 出来レース(既定受注者の内定) | 見積もり公募をしても、すでにどの業者を受注させるかが内定していて、他社は“当て馬”的に高値見積もりを出すよう誘導される。(ダイヤモンド・オンライン) |
| バックマージン/リベート | 施工業者が、契約額の一部を管理会社やコンサルタントに“裏で”渡す。工事費用に上乗せして請求する形になる。(アシストオール) |
| 見積もりの調整・統制 | 各社見積もりを事前にコントロールして、“似たような金額”を提示させる。価格差がほとんどない見積もりが複数出てくる。(アシストオール) |
| 設計コンサルタント・管理会社を通じた誘導 | 発注者(管理組合)と業者の間に入る設計・監理コンサルタントが、特定業者を推す、推薦する、見積もり作成段階で誘導する、など。(mansion-support.jp) |
| 相見積りすべてが不正に絡むケース | 複数業者に見積りを出しても、すべての業者が談合に関与しており、比較しようがない。(カシワバラライフ) |
これらの構造が組み合わさることもあり、被害を見抜くのが非常に難しいのです。
リスク・デメリット(管理組合・住民側にとって)
- 支払額が過剰になる
適正価格より高い金額を支払うことになる。余剰分が裏に流れる構造があるため、実質的な損失になる。 - 工事の質・内容が不透明になる
価格競争が抑制されると、質の良い施工よりもコスト重視・妥協施工になるリスクがある。 - 将来の追加請求・変更請求が行われやすい
受注後に追加工事・変更工事を提案しやすく、不利な条件で受け入れざるを得ない状況をつくれる。 - 信頼・ガバナンスの崩壊
管理組合に対する信頼が失われ、理事会・住民間での対立・不信感が強まる。 - 法的・行政的リスク
談合が認定されれば業者・設計事務所・管理会社に課徴金などの処分が科される可能性がある。(mansion-support.jp)
管理組合が加害を被った側として、損害賠償請求などを検討せざるを得ないケースも出てくる可能性があります。(mansion-support.jp)
なぜ発覚しにくいのか/居住者・管理組合側が気づきづらい構造
- 専門性の高い分野
修繕設計・建設工事の詳細を住民がすべて理解するのは難しい。技術的な裏付けや見積もり内訳の妥当性を判断するのは専門家でないと難しい。 - 情報非対称性
管理会社・コンサルタント側は業界知識・過去実績などを有しており、住民には“善意”を装い情報をコントロールできる。 - 表面的には適正に見せかけられる
見積もり文書・競合他社からの見積もりを提示しても、すべてに不透明性が含まれていれば比較そのものが意味をなさない。 - 既成慣行・業界慣習
「コンサル会社に業者紹介を任せる」「管理会社の推薦業者を使う」といった手法がかつてから普通に行われてきたマンション業界の慣習と重なる。
住民・管理組合がとるべき対策・チェックポイント
以下は、談合・癒着リスクを低減するための現実的な対策・チェックポイントです。
| フェーズ | チェック/手段 | 意図・狙い |
|---|---|---|
| 業者選定前準備 | 複数社からの相見積もりを必ず取得 | 競争を確保し、価格比較できるようにする |
| 見積もり内容の内訳(単価・工数・材料質など)を詳細に求める | 単純な総額比較では不正を見抜きにくいため、内訳まで開示させる | |
| 提案方式(プロポーザル方式など)を採用 | 金額だけでなく提案内容・仕様・施工方法で比較できるようにする | |
| 契約前に「談合違約金特約条項」を入れる | 談合が発覚した場合の違約金を契約に定めることで抑止効果を持たせられる (横浜マンション管理・FP研究室) | |
| コンサルタント選定を慎重に(利害関係をチェック) | コンサルが特定業者と癒着している可能性を排除する | |
| 第三者(外部専門家、建築士、マンション管理士など)に見積もりチェックを依頼 | 住民側の目を入れることで偏りを是正できる | |
| 見積もり比較・分析段階 | 複数社の見積もりが「金額も内訳も極めて似ている」場合は警戒 | 同じ単価・工数構成が複数社で揃っているのは不自然な可能性あり |
| 入札辞退や応募業者数が著しく少ないかを確認 | 意図的に競合を外している可能性を疑う | |
| 過去に同じ業者が連続して落札していないかを確認 | 常連業者という状況が談合の温床になる | |
| 質疑応答や見積りの修正・補足をきちんと行う | 曖昧・形式的な対応しかされないなら不正の可能性を疑う | |
| 契約時 | 談合違約金特約条項を明記 | 契約解除・違約金請求の根拠を持たせておく |
| 契約条件・仕様・保証内容を詳細に定める | 曖昧さを排除する | |
| 工事実施中・完了後 | 工事進捗・変更工事の妥当性を監理・監督 | 追加請求や変更内容をチェックし、妥当でないものは差し戻す |
| 住民・理事会への透明な報告・説明 | 不信感を防ぎ、チェック機能を働かせる | |
| 完了後、実際の出来高と契約仕様との差異を精査 | 手抜きや仕様変更を見逃さないために |
総括・見解
- 「管理会社と特定業者との癒着・談合」は、業界・報道レベルでも現実性のあるリスクであると多くの情報源が指摘しており、最近では公取委の立ち入り調査も起きている事実があります。
- ただし、それがすべてのマンション・すべての工事で起きているわけではなく、「疑わしいかどうか」を判断できるかどうかが鍵です。
- 最も有効な対策は、「透明性」「競争性」「複眼的なチェック体制」を設けること。住民・管理組合も無知・受動的であってはいけず、主体的にチェックする視点を持つ必要があります。
Audible(オーディブル)は、プロのナレーターが朗読した本をアプリで聴けるサービスで、「聴く」読書になります。Audible会員なら定額で12万以上の対象作品を聴き放題。※30日間の無料体験を試してみる。詳細は下記のURLをクリック!!







